
小中大
2016年 3月 18日16:51 編集者:兪静斐
作者:銭暁波
永井荷風がたまらなく好きである。
なぜこんなに魅かれてしまうのだろう。そう思って理由を並べ始めてみると、あれもこれもと浮かんでくる。すべて紹介したいのだけれど、紙幅の都合上、今回は一つだけ挙げることにする。山高帽を被って、黒のスーツを身に纏い、片手に蝙蝠傘、もう一方の手にボストンバッグを持って立つ荷風が目の前にいる。東京を微笑みながら散策する荷風を写し撮ったこの一枚が私のお気に入りである
谷崎潤一郎と並んで(谷崎を文壇に送り出したのが荷風である)日本耽美文学の巨匠である永井荷風は、『地獄の花』(1902年)『すみだ川』(1911年)『腕くらべ』(1918年)『濹東綺譚』(1937年)などの名作で知られている。また、1917年9月16日から、死の前日の1959年4月29日まで綴られた日記集『断腸亭日乗』は、大正から昭和にかけた日本の激動期の世相に対する時評、文学評論、また個人の趣味など膨大な量を誇り、日本近代文学を語る貴重な資料として荷風の最大の傑作といわれている。
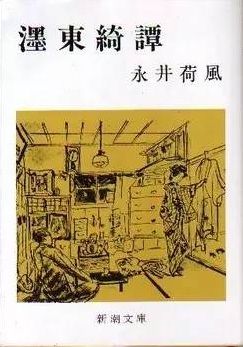
荷風は東京の街をこよなく愛した。散策するとき眺めていた街の風景や出会った人びと、またそのときの心情を荷風ならではの美文調で書き綴った。例えば『伝通院』の一節を抜粋してみよう。
「夕暮よりも薄暗い入梅の午後牛天神の森蔭に紫陽花の咲出(いづ)る頃、または旅烏(たびがらす)の啼き騒ぐ秋の夕方沢蔵稲荷(たくぞういなり)の大榎の止む間もなく落葉する頃、私は散歩の杖を伝通院の門外なる大黒天の階(きざはし)に休めさせる。その度に堂内に安置された昔のままなる賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)の像を撫ぜ、幼い頃この小石川の故里で私が見馴れ聞馴れたいろいろな人たちは今頃どうしてしまったろうと、そぞろ当時の事を思い返さずにはいられない」。
無尽の哀愁を漂わせる過ぎ去り日を述懐するこの一節、何度読み返しても飽くことがない。
東京の街を歩くことを好んだ荷風は、とりわけ隅田川を東に渡った深川、本所、向島などいわゆる下町が好きであった。
荷風は下町の出身ではなく、家柄は立派であった。外祖父は江戸時代の儒学者の鷲津毅堂で、父親の永井久一郎は文部省会計局長まで勤め、のちに日本郵船株式会社上海支店長に転身した、いわゆるエリート官僚の天下りであった。父親はまた禾原という号をもつ漢詩人としても知られ、明治漢詩界の重鎮である森槐南や、岩渓裳川(荷風は裳川の下で漢詩を習った)などとも親交が深かった。
では、いわゆる山の手の出の荷風は、なぜ「河向こう」の下町が好きなのか。
これもまた、次回語っていきたい。
